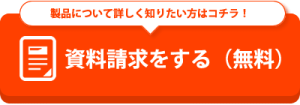要注意!毒きのこによる食中毒を防ぐために知っておきたいこと
きのこの生態について

きのこは秋の味覚の一つとして親しまれていますが、実はその中には食中毒を引き起こす毒きのこも存在し、場合によっては命に関わる危険があります。
自然界では、きのこは「分解者」として重要な役割を果たしています。きのこは木材を分解し、セルロースやリグニンといった成分を土に戻すことで「森の掃除屋」として機能しています。また、マツタケのように生きた松の根と共生し、糖類や無機養分の交換を行う「共生菌」としての役割も果たしており、森林の維持に貢献しています。このような関係性から、きのこは「木の子」とも呼ばれているのです。
毒きのこによる食中毒
毒きのこによる食中毒は全国で毎年発生しており、平成26年から令和5年までの10年間で240件、患者数は632人に上ります。年間平均で24件、約63人が被害にあっている計算です。
特に注意すべき毒きのこには以下の種類があります:
- ツキヨタケ
- クサウラベニタケ・イッポンシメジ
- テングダケ・イボテングダケ
- カキシメジ
これら4種類が毒きのこによる食中毒の約77%を占めており、毒きのこを正しく理解して誤食を防げば、8割近い食中毒が防げると言われています。特に、食中毒の多発時期である9月・10月は、毒きのこの発生が増えるため、十分な注意が必要です。
食中毒を防ぐために
厚生労働省では、食中毒を防ぐために次の4つを推奨しています:
- 採らない
- 食べない
- 売らない
- 人にあげない
見た目や色で判断することは非常に危険です。発生場所や環境により、同じきのこでも形や色が変わることがあるため、誤った判断をする可能性があります。少しでも疑わしいきのこは、食べないことが一番安全です。