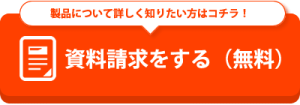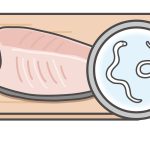
2022年の食中毒統計では、アニサキスが原因となった事例が全国の約6割を占めるまでに増加しています。近年では特に日本海側での発生件数の増加が注目されており、地域的にも「これまで安全」とされてきたエリアでのリスクが再認識されています。
気温上昇と食中毒リスクの関係
気温が上がると、細菌性の食中毒リスクが高まることはよく知られていますが、実は寄生虫による食中毒にも気温は深く関わっています。とくにアニサキスの場合、海水温の上昇や海流の変化によって魚の回遊ルートが変わることで、これまで生息していなかった地域にも「リスクの高いアニサキス」が広がる可能性があるのです。
実際、過去には黒潮の蛇行によってカツオの漁場が変化し、それに連動するかたちでアニサキス食中毒の発生地域にも変化がみられた事例があります。
さらに、夏日を記録する日が早く訪れるようになった近年では、魚の鮮度管理や保存環境が悪化するリスクも高まり、家庭でも飲食店でも食中毒の危険性が一層高くなっています。
アニサキスとは?
アニサキスは線虫の一種で、魚介類に寄生し、人が摂取することで胃や腸に強い痛みやアレルギー症状を引き起こす寄生虫です。
主にサバ、アジ、サンマ、カツオ、イカなどに寄生し、生食や加熱不十分な魚介類が原因となることがほとんどです。
なぜ日本海側で増えているのか?
これまで、日本海側で主に見られていたA. pegreffii型(Ap型)のアニサキスは、筋肉への侵入が少なく、内臓ごと廃棄されることで食中毒リスクが低いとされてきました。
ところが近年では、太平洋側で食中毒を引き起こすA. simplex(S型)が、日本海側でも確認されるようになり、「日本海側の魚は比較的安全」という従来の認識が通用しなくなりつつあります。
飲食店に求められる対策
飲食店においては、「新鮮な魚=安全」という誤解に注意し、下記のような対策を徹底することが重要です。
冷凍処理:−20℃で24時間以上の冷凍でアニサキスは死滅
加熱処理:70℃以上、または60℃で1分以上の加熱
目視確認:専用ライトや黒いまな板で白い虫体を発見しやすくする
器具の使い分け:交差汚染を防ぐ包丁・まな板の分離
特に、サバを生で提供する「ゴマサバ」などの料理を扱う店舗では、冷凍済み原料の使用や提供時のリスク説明なども信頼確保のポイントです。
一般の方にも知っておいてほしいこと
家庭でもアニサキス対策は可能です。スーパーなどで購入した魚を生食する際には、以下の点を心がけましょう:
「生食用」と表示された冷凍済み製品を選ぶ
自宅で冷凍処理を行う際は−20℃で24時間以上
切り身の断面に白い線状の寄生虫がいないか目視で確認
まとめ
気温上昇に伴って増加するアニサキス食中毒。日本海側でもリスクが拡大しており、地域や魚種にとらわれず、日常的な注意と対策が求められています。
飲食店においては、お客様の安全と信頼を守るためにも、基本に立ち返った衛生管理と情報提供の工夫が重要です。
出典:
- 国立健康危機管理研究機構(Japan Institute for Health Security:JIHS)(https://www.niid.jihs.go.jp/)